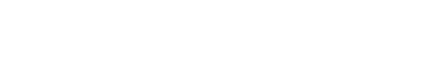文化と芸術の中の狂気
アジズ・アリ・ダード / Aziz Ali Dad(パキスタン)
ライター / コラムニスト / 社会科学者 / 2018年度ALFPフェロー
創造性は普遍的なものだが、一部の文化的エートス(精神)や思考様式は創造のプロセスに影響を与える。パキスタンでは、芸術家や詩人や文学者の大半が、創造的な職業に対してまるで見当違いな概念を抱く傾向にある。それは結果的に、狂気、奇矯な振る舞い、あるいは思想への憎悪を称える風潮をもたらしている。神秘的に物事を捉えることは、パキスタンの文化的エートス、認知機能、認識論的構造の一部であるため、人々は感情に思想を求め、思想から感情を得ようとする。ゆえに彼らは感情を満たしてくれるような考えに飛びつく。神秘的な見方に影響を受けた人々の心は、外在の現実を主観的な色に染め、主観的な現実と客観的な事実とのはざまで混乱してしまう。
創作活動は主観的な性質のものであるがゆえに、詩人には認識規範と文学的慣習を破ることが許されている。世の中には確立した規範を侵すことが許される特例が設けられており、詩人の特権もその一つである。この免責された特権によって、時として芸術家は、非合理と狂気を排斥している領域の中へ入り込む。それはバランスを維持するのがきわめて難しい不安定な領域である。シャキーブ・ジャラーリ、サラ・シャグフタ、アンス・モイン、サルワット・フセイン、ムスタファ・ザイディ、ジャウン・エリアといったウルドゥー語詩人たちは、正気と狂気の境界に佇み、不気味な領界に棲む追放された狂気の半自我と、理性が司る正気の世界とを繋ぐ通路を開削している。
ペルシャ語とウルドゥー語の文学の伝統においては、心臓に受けた傷という隠喩(「心臓の血」「心臓の傷跡」など)が、創造の源や純粋な感情を表す象徴として見なされる。現代では、高名なウルドゥー語詩人ジャウン・エリアの詩の中に血の表現が多く見られる。彼の傷は、伝統的文学の中に出てくる傷とは異なり、今日、伝統に幻滅させられながらも、代わりを見つけられずにいる悲哀の経験によるものである。
ジャウン・エリアの詩には、血や喀血のイメージが頻出する。心理学的に言えば、それは、追放された半自我が内的世界に構築する狂暴な世界の表れである。この正気と狂乱との間の内的抗争が、詩人を二つに引き裂く。彼の叫びは、ミシェル・フーコーの言葉を借りれば、理性的な社会から追放され、狂人と病人と犯罪者の収容所に追いやられた人間の叫びである。その追放された自我は傷つき、正気の弱った皮膚からは血が滲み出ている。そして、そこで血は死の象徴となる。エリアは次のような詩を書いている。「私の内部の門は外から鎖され/私は自分がニュースであるような自己の中には生き得ない/傷だらけだが血の痕はない/狂暴な自我が血を抜かれたとき、自我とは一体何者になるのか」。また他の詩ではこうも言っている。「私の睫毛には血が飛び散っており、顔面は蒼白だ/こんな変わったことをする心臓こそ私の無二の自我」。
パキスタンの芸術家たちのもう一つの傾向は、創造の閃きを得るために、自由奔放なライフスタイルに浸り、神秘的な方法を用い、苦悩を抱懐することである。彼らのだらしない姿や心ここにあらずといった様子は、何か純粋なものの創造に没入している証しだと考えられている。しかし芸術家らしい風采にのぼせ上り創造性が疎かにされているケースも多々見られる。芸術家には自分の創造の場と表現の自由が必要であることは無論だが、それを隠れ蓑として放逸が助長されるのは問題である。結果として、芸術と文学から思想が消えてしまう。また、あるひとつの態度が芸術家のアイデンティティとして受け取られると、それは仮面として機能する。そして仮面は、着けているうちに次第に内面に食い込み、ついには内的自我を乗っ取ってしまう。仮面舞踏会は、実質も意味も持たない、内面の空虚を隠すためだけの芝居にすぎない。芸術において仮面舞踏会的な要素が支配的になればなるほど、実質も意味も薄らいでいく。
パキスタンの文学・芸術の問題の一部は、文学・芸術界の慣行と、芸術家が内面化している知的環境にある。芸術家たちは、芸術界や文学界の長老たちの間で広く行われている慣行を、自分の知的環境の一部として受け入れる。詩人や芸術家であることは、悲しみを糧とする失意の人として、薄汚い服に身を包み、狂的で自由奔放な生活を送ることを意味する。一般社会においても、芸術家は知的思考を疑い、既成観念を打ち砕く人という通念がある。このように、パキスタンの芸術家や作家が育つ文化的、知的メカニズムは、無気力で鬱屈した精神によって作られた神話に基づいており、真に斬新なものの創造や創造的な思索に伴う苦難のプロセスを避けている。つまり彼らは、規範や組織化された知識の縛りから逃れているのである。
イマニュエル・カントも、芸術的天才は神秘的な存在であって、いかなる規範にも縛られないと述べた。そこが芸術と思考が分岐した歴史的時点であったが、時代が進むにつれ、その分岐は大きな裂け目となり、そこに創造性についての神話や誤った見方が蔓延することとなった。主観的で気紛れな着想と無意識裡の錯乱が極端なレベルにまで達すると、芸術家は、直感、幻想、空想、幻影、妄想、陶酔、迷妄、想像力、幻覚などを識別する能力を失う。その結果、宗教的経験が恋愛経験と、空想が想像と、幻覚と現実とが混淆してしまう。
社会的レベルでは、それはカルト宗教や、時間・空間についての妄想の形をとって現れる。〈思考〉と〈詩〉の間での対話や交流は行われず、裂け目は広がる一方である。文学批評は文学や芸術を思想の世界とつなぐ役割を担っているにもかかわらず、パキスタンの作家たちは、文芸批評家を、自分では歩けないのに他人に歩き方を教えようとする人間だと非難している。しかしそもそも芸術家の中に崇高な思想がなければ、崇高な芸術の境地など望むべくもないではないか。情感の暗い雲が理性を包み込んでしまうと、暗がりから生まれてくる数々の魔物が思考を貪り食べてしまう。狂気のみを糧にすれば、社会、政治、道義、宗教は堕落する。パキスタンにおける腐敗の蔓延、理性的思考の嫌厭、自爆テロ、宗教的抗争は、正気の道を逸脱した文化が呈する症状である。文化を狂気から癒すには、芸術と社会における狂乱の筋書きを奨励するのではなく、美しい思想を育んでいくことが必要不可欠である。
※本記事の内容や意見は著者個人の見解です。